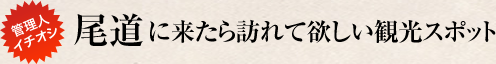![]()
芸州藩の御用商人であった天満屋(富島治兵衛)の二代目天満屋浄友は塩浜築造を藩に願い出て、延宝五年(1677)藩のバックアップのもと備後御調郡富浜村に富浜古浜と呼ばれている塩浜を完成させた。
その塩田を経営して隆盛を極めた三代目天満屋吉兵衛はその財力で延宝七年(1679)、烏崎(からすざき)一円(現在の尾道市向島西富浜地区)を庭園として「海物園」と名付けた別荘を建てた。
現在、その跡地に胡子神社が鎮座する浮島を見ることが出来る。
この庭園内に移築された茶室は、もともと伏見城の織部屋敷にあって、古田織部が作事した最古の燕庵の写しで、太閤秀吉も愛用していたものと言われている。
その後、この茶室は織部屋敷から本願寺に移築されていたが、十六世紀後半~十七世紀前半に広島藩の浅野公が拝領していたものを天満屋吉兵衛が譲り受け、京都から海物園に移築したものである。
そして文化十一年(1814)、四代目天満屋昭(しょう)亘(せん)は当時の浄土寺住職と親交が深く、住職のたっての願いにより、この海物園の茶室を浄土寺境内に奉納移築した。
この浄土寺にある燕庵の破風には「燕」の文字の扁額が掛かり、三畳台目の茶室、炉台目切、燕庵の象徴である相判席の外、水屋の本席と四畳・四畳半の勝手、台所よりなっている。
本席は三畳台目と狭い茶室であるが、意外に広く感じられる。
織部の工夫により八ヶ所の窓が取り付けられ、明るい感じの設(しつら)えである。
本席と勝手間は約三十五度屈折して接続しており、四畳の板床には小堀遠州の筆による「露滴庵」の墨蹟が掛かっている。
外観は一重の入母屋造、茅葺(かやぶき)、軒下の一角が土間(どま)庇(ひさし)となっており、勝手の間の二室は浄土寺への移築時に建増しされたものである。
庭園は方丈の「勅使之間」に面して作られたもので、築山泉水庭園である。
文化三年(1806)、徳島の隠士(いんし)で雪舟の十三代の孫、長谷川千柳の作庭になるもので、庭石には仏の名がつけられており、庭に仏世界を表している。
この燕庵の本歌(始めに作られたもの)は安土桃山時代、古田織部が住んでいた現在の京都市下京区西洞院通正面下ルにある藪内家の家元の邸内にあった。
この藪内家の当主は茶の湯の師祖である武野紹鷗(たけのじょうおう)の「紹」の字をもらって、代々紹(じょう)智(ち)を襲名している。
その武野紹鷗の門人で千宗易(利休)の弟弟子であった剣仲紹智を流祖として、現在まで四百年歴代の家元が古儀茶道藪内流の茶風を守っている。
又、剣仲の道号(禅僧が一定の法階に達し、本師から授与される称号)は大徳寺三玄院の開祖である春屋宗園和尚から授かったもので、菩提寺として歴代家元の墓も三玄院にある。
剣仲紹智は天正九年(1582)九月二十日、千宗易(利休)を媒酌人として古田織部の妹のせんと洛北紫竹町で祝言を挙げている。
織部より剣仲のほうが七歳年上の義弟であった。
織部は東軍として大阪夏の陣に出陣の際、自分が住んでいたこの京屋敷を剣仲に譲り渡している。

燕庵(京都市下京区)
元冶元年(1864)、蛤御門の変の兵火で屋敷と共にこの茶室も扁額(伝・村田珠光筆)を残して焼失してしまい、天保三年頃(1831)、建てられたという摂津有馬の武田家(武田儀右衛門宅)にあった燕庵の写しを慶応三年(1867)に移築したものが、現在の藪内家の燕庵の写し「篁(こう)庵(あん)」である。
この篁(こう)庵(あん)の内部は三畳台目に一畳の相判席を設けた織部好みの茶室、床を正面にして右手には反古(ほご)襖(ふすま)の茶道口、左手には給仕口と相判席が配されており、通常は二本襖をたて、三畳台目として使う。
しかし貴人を招くときは襖をとって、欄間を取り付け、畳を取って円座を敷き、敷居より内を上座、相判席を下座とし、茶室に上段と下段を設えた。
客が大人数のときは二本襖を外して客座を広げることも出来る。
又、茶室と同じ様に腰掛にも貴人と相判の席を分ける仕組みが細工されている。
千利休の侘び茶の精神が、人が腰を屈めなければ入れないほどの躙(にじり)口、二畳にまで縮小した狭い空間と藁を練りこんだ荒壁で塗り固めた床、黒楽の茶碗、黒漆の茶入れといった求道的な世界に入り込んでいったのに対し、古田織部の無骨でユニークな人柄は「ひょうげもの」と呼ばれ、何人(なにびと)も平等であれという利休の考えとは違って、貴人口、相判席を設け、色は黒でなく色彩豊かなもの、形は真円でなく作為的に歪(ひずみ)さえ入れた茶碗を好み、日の移ろいや、簾の掛け外しによって窓を通して室内に多彩な明りを採る方法を考案した。
まさに自由闊達な桃山時代の文化そのものである。
当時の正統な利休の門人にすれば「茶の湯の作法も分からぬ異端者め」と眉をひそめた者もいたようであるが、「ならひ無きを極意とする」という利休のオリジナリティこそ大切なものであるとの教えを地でいったのが織部であったと言える。
利休が靜中に美を求めたのに対し、織部は動中に美を捉えようとしたのである。
利休とは異なる要素を茶の湯に取り入れながらも、今では利休の茶の湯に少しも背くものではないと高い評価が定着している。
織部が始めて利休のわび茶に出会った時、織部は茶の都会的で洗練された美の真髄にせまる利休の偉大さに心服した。
それ以来利休を師としてきた。
利休も織部の才能を見抜き、利休自身私の後継者は織部であることを他言して憚らなかった。
利休は織部のことを「考える前に体が動いてしまう性格であるが、愛すべき機智に富み、打てば響く人情家で、機微も解かり一角の鑑識眼の持ち主である」と述べている、師の利休に高く評価された織部は、利休が罪を得て堺へ蟄居を命ぜられた時、淀の川辺に細川忠興と共に舟で下っていく利休を見送っている。
時の権力者太閤秀吉に背いた利休を見送るという危険を犯してまで、自分を評価してくれた人に恩義を果している。
利休は川辺の二人を見つけ、送られていく舟の上から静かに手をあわせたという。
人が人を知るということなのであろう。

浄土寺露滴庵(尾道市東久保町)
秀吉が自らの隠居後の住まいとした伏見城の築城にあたって「利休が行っていた町衆の茶の湯を武家風に改めよ」と織部に作事するように指示しているが、利休の自刃後第一人者となっていた織部が独自の道を追求していく過程で、伏見城に相判席付きの燕庵を作ったことは十分考えられる。
徳川の世になって織部の茶が持つ「精神の自由」が家康の考え方と合わなかったのか、織部の重臣木村宗喜に家康および将軍秀忠の暗殺を企てたとの嫌疑がかけられ、上司であった織部はこの事について一言も弁明せず切腹して果てた。
七十三歳であった。
墓は大徳寺三玄院にある。
京都では上京区の三千家(表・裏・武者小路)を上流の茶と呼ぶのに対して、下京区の藪内家は下流の茶と呼ばれている。
その藪内家は代々西本願寺の保護を受け、現在十四代宗家となっている。
豊臣秀吉を祀る豊国神社(京都市東山区大和大路通正面茶屋町)の例祭は九月十八日(旧暦八月十八日秀吉の命日)に行われるが、献茶式は藪内家によって執り行われている。
京都駅からさほど遠くない所であるが、藪内家は当(まさ)に市中の山居といった趣であるが、若宗匠(現十四代家元)は露地の手入れの際の蚊の多さには閉口するのですよと笑っておられた。
尾道は江戸時代、北前船の寄港地として港を中心とした物流の中継基地として栄え、その活発な経済活動を通じて財を成した豪商達が競うように茶園(さえん)と呼ばれる別荘・庭園を林立させた。
橋本氏(加登灰屋)の爽頼(そうらい)軒(けん)、葛西家(泉屋)の賀島園、富島家の海物園など大小の茶園が点在していた。
又、尾道市長江の山城戸には把(ゆう)翠(すい)園(えん)という熊谷氏(屋号・金屋(かなや))が営んでいた茶園があり、その敷地内の登り窯では、主に「御庭焼」という煎茶器を焼いていたことも明らかになっている。
尾道ではこれらの茶園を舞台にして茶の湯を嗜(たしな)み、文人墨客との交わりも盛んに行われていた。
茶園文化が花盛りを迎える江戸時代後期、薮内流がまず尾道にもたらされ、尾道から同門の宗匠(そうしょう)として茶人内海(うつみ)自得(じとく)斎(さい)を輩出するなど同流派が尾道に於ける茶の湯の主流を形成するに至った。
内海自得斎は、現在の尾道市東久保の山王社(山脇神社)参道の入口辺りに住んでおり、自得斎の庵には頼山陽や田能村竹田等の文人墨客、地元では橋本竹下などの尾道商人が出入りし、サロンを形成していた。
幕末頃、速水流の三代目家元速水宗(はやみそう)筧(けん)が来尾すると早速、尾道の豪商・天野家の主人天野半次郎・天野嘉四郎(尾道町年寄同格・諸品会社頭取)が入門し、天野家を中心として同流派が尾道に広がっていった。
天野家は明治時代に入っても尾道の政財界の重鎮として尾道の第三黄金時代を築き上げた。
近代以降になると尾道女学校の授業での茶道が裏千家を採用したこともあって、裏千家流の茶道が尾道に浸透し、尾道の茶の湯は更なる広がりをみせていくことになった。

春夏秋冬。季節ごとに尾道は様々な顔を見せてくれます。
歴史的な名所を訪れるのも良し、ゆっくりと街並みを歩きながら心穏やかな時間を過ごすのも良し、美味しい食事を心ゆくまで楽しむも良し。
大人な遊び方ができる尾道において「尾道に来たら、ココだけは行って欲しい!」という、管理にイチオシの観光スポットを紹介しています。詳しくはこちらのページを読んでみてください。
>>管理にオススメの観光スポット