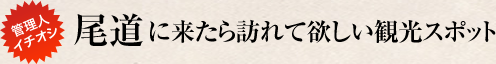![]()
平田玉蘊は天明七年(1787)、尾道の木綿問屋福岡屋の次女(長女は早世)として生まれた。
名は豊(とよ)、または章(あや)といい玉蘊はその号である。
現在の尾道市の本通り商店街、これが当時の西国街道で、三井住友銀行のあるあたりに当時尾道町奉行所があった。
その西側に奉行所の管理していた米蔵があり、山陽道をはさんでその北側が福岡屋で、福岡屋の西側南北に一里塚を示す松が植えられていた。このため福岡屋は「一里塚の福岡屋」と呼ばれていた。
当時尾道には北前船が寄港し、他国の廻船が入港するなど町は活況を呈していた。
その経済的発展の中で、尾道には財を成す多くの豪商が出現していた。
福岡屋もその内の一つで、浄土寺(尾道市東久保町)に収蔵してある安永三年(1774)製作の「安永の屏風」には福岡屋の敷地に「福岡屋新太郎抱(かかえ)」と記してある借家が六軒あり、敷地全体の三分の一を占める北側は「福岡屋新太郎庭」と書かれている。
これは当時珍しい高価な蘇鉄が植えられていたので特にこれをこのように示したようである。

福岡屋(平田玉蘊生家)付近
父新太郎(五峯(ごほう)はその号)は家業のかたわら能楽や茶や歌に通じ、特に舞には神が宿るとさえ讃えられていた文化人であった。
そんな何不自由のない家庭の中で五歳下の妹玉葆と共に池大雅の門人で尾道の福原五岳や応挙門下の八田古秀に画の手ほどきを受け、さらに漢詩は神辺の菅茶山、儒学は竹原の頼春風に師事して一流の学問を身につけていた。
ところが文化三年(1806)、玉蘊が二十歳の時、父五峯が四十七歳で亡くなり状況が一変する。
大黒柱を失って福岡屋は除々に左前となっていくが、長女としての玉蘊は家業の存続・再建を図ることはなかった。
養子をとって家業の存続・再建するよりも画業でどうにかして身を立てようと考えていた。
次の年の九月、玉蘊は玉葆と共に竹原の照蓮寺で開かれた頼家の法事に招かれた際、運命の人、頼山陽と出会うこととなった。
玉蘊この時二一歳、山陽二九歳であった。
座興で玉蘊が描いた絵を見て山陽は「絶塵風骨是仙姫(ぜつじんのふうこつこれせんき) 却画名花濃艶姿(かえってえがくめいかのうえんのすがた)」(汚れを知らぬ気品はまさに仙女、この人がこんなあでやかな牡丹の絵を描くなんて)「淡粧素服(たんしょうそふく) 風神超凡(ふうじんちょうぼん)」(薄化粧で品の良い装いのたぐい稀な女性である)と玉蘊を一目見て心を奪われてしまった。
山陽は脱藩騒動を起こして京都から連れ戻され、その後三年間は座敷牢で幽閉され、出されてから二年の謹慎生活を終えたばかりであった。
そんな山陽にとって玉蘊は眩しく、仙人のように思えたのであろう。
山陽の父春水(しゅんすい)は脱藩をした山陽を廃嫡し、弟春風(しゅんぷう)の子景譲(けいじょう)を養子として迎え、家の存続を図った。
山陽の将来については親友であった神辺の菅茶山に、茶山が自ら開いた四書五経を中心とした講釈がなされている黄陽夕葉村舎(こうようせきようそんしゃ)(廉熟(れんじゅく))の都講(とこう)(塾頭)として迎えてもらい、子供の無かった茶山の養子として菅家を継ぎ、いずれ福山藩に取り立てられないものかと考えていたのであった。
一方、山陽は何時(いつ)か三都のいずれかに出て世に名を成し、志を果たしたいとの思いから、広島を離れることはそのまず第一歩であると考え、都講(塾頭)になることを承諾した。
そして文化六年(1809)十二月、山陽は広島を発ち、神辺で廉塾の都講(塾頭)となった。
神辺は思い焦がれている玉蘊のいる尾道に近いこともあった上に、玉蘊が神辺の菅茶山と懇意にしていたことも決め手となった。

平田玉蘊絵碑(持光寺内)
儒学者として茶山を山陽は尊敬していたが、それ以上に都へ出たいとの思いは強く、そのことを玉蘊に会って伝えた。
「近々わしは廉塾を飛び出して、京に行くつもりじゃけぇ、一緒についてきてくれんかのう。玉蘊殿にとっても京は絵の先生もおるし、夢を実現させる舞台じゃと思うがのう」
「でも、私には母や妹が・・・」
「京で家塾を開いて稼いでいくけぇ、御母上や妹御(いもうとご)も一緒に連れてくるとええ。面倒はわしが見ちゃるけん」
山陽は夫が竹を描けば、妻は蘭を描くというような夫唱婦随の夫婦を理想としていたので、玉蘊はまさにそのめがねに適(かな)う女性であった。
山陽は玉蘊との京都での新生活を想い描いて必死に申込んだ。
玉蘊は家に帰って、このことを母峯や妹玉葆に伝えた。
「借家の収入だけで昔のように贅沢は出来ひんけど、食べていくだけならなんとかなるけぇ、要領の分からん京で暮していくよりゃー、この尾道にいてお父さんと一緒のお墓に入りたいがのう。それにこの年になって山陽さんに気をつこうて暮していくのはいかがなもんかのう」
と峯は思いながらも、娘の願いも聞いてやりたいと茶山や知り合いに手紙を送って山陽の素性を尋ねた。
茶山からは「文章は無双であるが、年がすでに三十一歳にもなるのに世間ずれしていない。まだまだ人間的には子供であり、早く大人になって欲しいものだ」との返事があり、峯は逡巡していた。
しかし、妹の玉葆は竹原での詩会や忠海での舟遊びで山陽が玉蘊に好意を寄せていることを見て知っていたので前向きであった。
「久太郎さんはお姉ちゃんのことをすいちょるけん大丈夫じゃと思うヨ」
この玉葆の言葉が峯の背中を押すこととなり三人で京に向かうことになった。
文化八年(1811)二月、山陽は神辺を発ち上洛した。
そして新町通丸太町上ル春日町の借家に晴れ晴れしい気持ちで「頼久太郎僑(きょう)居(きょ)」との表札を掲げ「真塾」という名の家塾を開いた。
ところがしばらくして父春水の知り合いから、京に滞在するについては広島藩の一定の手続きが必要である。
勝手に塾を開いたり、表札を揚げたりしては広島藩としての面子が立たず、広島に連れ戻されて幽閉とのお咎(とが)めを受けることになる。
しかも、山陽本人だけでなく父の春水までも累が及ぶこととなるとの忠告があった。
山陽が神辺に行くのにあたっては広島藩の了解を得、又、京に出るにあたっては茶山の許可を得ているというのが山陽の理屈であった。
しかし、茶山は福山藩の人であり京の広島藩への届出はしていなかった。
山陽は二度目の脱藩扱いとなることを恐れ、慌てて表札を外し、塾は閉講し、大阪に一時身を隠した。
そして、茶山に改めて「出藩の表向きは茶山先生の名代である旨の書状を出して欲しい」と依頼した。
山陽は都講として「弟子は塩踏みじゃ」(足の裏に何も感じない)として十分な指導もしなかった上に「山は凡、水は濁、弟子は愚、師は頑」と墨で壁に書いて茶山のもとを黙って飛び出しており、これほどあつかましい申し出はなかった。
茶山にとって山陽が廉塾を去ったことについて「後足で砂を蹴り上げられた」との忸怩たる思いであったが、山陽の父春水との友情を優先させ「京阪住居の事、少しも差し支えこれ無く」と苦々しい思いで返事を書いた。
とりあえず、これをもってともかく京の広島藩への届出を済ませた。
しかし、正式に許可が出た訳でなく堂々と京で開塾することは憚(はばか)られた。
山陽は内心二度目の脱藩扱いとなって帰郷させられるのではないかと恐れていた。
このために京に入った時はいくばくかの金子があったもののたちまち窮してしまっていた。
こんな時に玉蘊親子が上京してきたのである。
山陽一人が食べていくのがやっとである状況の中で当然玉蘊親子の面倒まで見る余裕などなかった。
何の先の見通しの無いまま玉蘊親子のいる西本願寺の近くの宿坊を訪ねた。

西本願寺御影堂
「久しぶりじゃのう。よう来たのう」
「久太郎様のお話を頼ってこうして三人で京に参りました」
「実はのう正直に言うと塾は開いたのじゃが、広島藩の正式な許可が出ぬうちは表立っての活動が出来んのじゃ。早く許可が出るのを待っているのじゃが、一向に返事がこんのじゃ。じゃけえもう少しだけ待ってくれんかのう」
山陽は初めて会う峯と目線も合わせられずにいた。
それほど山陽は煮え切らなかった。
他人行儀に「もう少し」を繰り返すのみで結局、山陽は逃げるように春日町の自宅に帰った。
玉蘊は動揺を隠せないでいた。
どうしたら良いのか分からなかった。
表向きは姉妹で絵の勉強のために京に行ってくるということで尾道を出てきたのであるが、本音は山陽との婚姻をまとめるつもりであった。
玉蘊は山陽の返事を待っている間、福岡家の菩提寺である持光寺の本山の永観堂をお参りしていても、西本願寺の御影堂(ごえいどう)で吉村孝敬や徳力善宗・善雪父子の襖絵を写しとっていても、伊藤若冲の軍鶏図(ぐんけいず)の粉本(ふんぽん)(手本)を模写していても集中出来ないでいた。
峯は知り合いに「京の四条川原の夕涼みはほんまに涼しゅうて気持ちの良いものじゃが、こがいに毎日続くとかえって疲れてしまうけぇ、この日中の暑い時に尾道に帰るのは大変じゃけん、帰るのはもう少し後にしようと思うとるけん」と愚痴めいた手紙を送っている。
京での滞在を少しでも先延ばししてでも山陽からの良い返事を待っていたのである。
八月の終わりになり玉葆は「お姉ちゃん、尾道に帰ろうゃあ。返事はもうこんわ。あきらめにゃあ、いけん」と言い出した。
妹は覚めた目で状況を見ていた。
虚しく京から引き上げてきた玉蘊には「山陽を追っかけて京まで行って結局、山陽にふられた女」との噂がすぐに広島から備前あたりにまでも伝わっていて、恥ずかしくて何処にも出ることも出来ず、精神的にかなり参っていた。
久太郎殿とうまくいかなかったのは「時節が未だ至らなかっただけだわ」と諦めるようにして私にはこれしか生きる道はないとかえって一心に筆を取って絵に集中して山陽のことを忘れようとした。
この頃玉温が描いたのではと言われる絵が尾道の浄土寺に残っている。
庫裏の玄関の衝立にそれは配されており、「軍鶏図」と題されて下地を金箔とし、中央の岩の上に寒風に向かって立つ一羽の痩せ細った軍鶏(しゃも)を描いている。
どんなに強い寒風が吹こうが岩の上に足先を踏ん張って立っているその軍鶏の姿は、なんとしても画で家族を支えていこうとする玉蘊の姿とだぶって映る。
(注・この衝立の裏面には円山応挙の弟子で四条派の祖である松村呉春による花鳥画が合装されている)
そうした表も出られぬほどの玉蘊を救ってくれたのが、たまたま尾道に逗留していた伊勢の俳人白鶴鳴(ばいかくめい)であった。
山陽との傷を癒すためにか玉蘊は末松山波も越えなんと将来を約束し、一子をもうけたが夭逝(ようせい)してしまった。
このことが鶴鳴にとってショックであったのか、どこか心の底で山陽のことを忘れきれないでいる玉蘊を疎ましく思ったのか、やがて鶴鳴も玉蘊のもとを去ってしまった。
山陽は尾道の豪商橋本竹下に「玉蘊は鶴鳴に弄ばれた」と玉蘊を非難する手紙を送っているが、「憐れむべし、我実に背(そむ)きおわんぬ」と一番誠意が無かったのは自分自身であることを十分承知していた。
こういうことがあって玉蘊はそれまで以上に強くしなやかな女性に変わっていった。
妹の玉葆の子玉甫を養子として迎え入れ、工夫研鑽を重ね、常に新しさも採り入れることを怠らず、どんなことがあっても絵筆一本で母を養い、家を守って自立していくことを決意していた。
当時尾道では豪商を中心とした茶園文化が花開いており、絵の依頼があれば、詩会や茶会にも積極的に参加するだけでなく、酒席にもはべらって絵を描いたことから文芸芸者呼ばわりもされたが、超然として絵を描くことで画料を得、生計を立てていたのである。
文政七年(1824)、玉蘊が描いた渡橋忠良(渡橋貞兵衛)翁像の肖像画がある。
渡橋忠良は元々宮原姓の竹原の人であったが、尾道で物産の仲介業で名を上げ、財を成した豪商であった。
山陽は預金をこの渡橋家に預け、今で言う財テクで利子収入を得たりするほど山陽との親交が深く、山陽が京都と広島への行き帰りによくこの渡橋家にも逗留した。
この縁で渡橋忠良の五男の宮原節庵が山陽に師事することになる。
この肖像画には落款(らっかん)が無いが、山陽はこれに「稿碑銘敬題」(敬って翁の功徳を述べる)と題した賛を記している。
これが玉蘊との最後のコラボレーション(共同作業)ではないかと言われている。

田能村竹田像 (尾道千光寺)
因みに渡橋家の墓所は尾道の千光寺観音堂の西側にあり、山陽の撰並びに書になる墓碑が建っている。
玉蘊が四五歳の天保二年(1831)、江戸で刊行された白井華陽著「画乗(がじょう)要略(ようりゃく)」の閨秀(けいしゅう)(女流画家)の部に二十二名の中に玉蘊は紹介され、さらに序には、代表的な女性画家として清原雪信(狩野探幽の姪)、池玉蘭(池大雅の妻)、桜井雪保(桜井雪館の娘)、江馬細香等と共に五人のうちの一人として玉蘊を「筆法勁秀(ひっぽうけいしゅう)、賦媚(ぶび)を以(も)って工(たくみ)となさず、名は三備の間に著(あら)わる」(筆遣いは力強く秀でていて、世間に媚びた技法では無く、美しいものを作り出す技を持っている。その名は広く知れ渡っている。)と、玉蘊の評価の高さが、全国レベルであったことがわかる。
天保四年(1833)、田能村竹田(たのむらちくでん)も「竹田荘師友画録」に玉蘊のことを語っており、「平田氏尾道の人なり。画を売ってその母を養う。その名前は全国に聞こえている。住まいしている所に蘇鉄が植えられているので、そこは鳳尾蕉(ほうびしょう)軒(けん)と名付けられている。画は京派より出て花鳥画を得意としている。優れた筆遣いや彩(いろどり)はともに素晴らしく、又、関羽像など人物画も勇壮で逞しい筆遣いである。玉蘊本人の容姿もたおやかで美しく、細くしなやかな宝石を削ったような華奢(きゃしゃ)な手指だからこそ言葉に言い尽くせない程の見事な画が描けるのだろう」と記している。
勿論、この時代、依頼されて描く絵だけでは家族を養っていけず、福岡屋に残っていた代々の古美術品は生計の足しにと散逸してしまったが、玉蘊は残されていた古鏡十数枚だけは心の支えとして最後まで手放さなかった。
山陽の叔父頼杏坪(らいきょうへい)は「古鏡歌」と題にして「金鈿(きんでん)銀笄(ぎんけい)欲する所に非ず、独り古鏡を撫でて潔行を持す」(彼女は金の簪(かんざし)も銀の櫛(くし)も望んではいない。
古鏡を撫でて清らかな日々を送っている)と、そんな真面目な彼女であるので災いは除き、幸せをもたれせておくれと念じている。
又、山陽は三十三歳の文政二年(1819)五月、玉蘊の所蔵する古鏡に題して
「一段傷心(しょうしん)誰得職(だれかしるをえん) 凝塵影裡 孤(ぎょうじんえいりこ)鸞舞(らんま)」(傷ついたあなたの心を誰が知っているだろうか。あなたに対して私は不誠実であった。ただ一羽の鸞(らん)(鳳凰の一種)が空を舞っているように寂しい境遇に追い込んでしまって、本当に申し訳なく思っている)と詠っている。
本心では山陽のことを忘れきれないでいる玉蘊にとって、この歌ほど辛いことはなかった。
あの時どうして事情を汲んでもう少し待ってあげられなかったのかと、今更のように自分を責めた。
その山陽も天保三年(1832)九月、結核で亡くなってしまう。
玉蘊が四十六歳のことであった。
天保五年(1834)、全国的な天保の大飢饉の際、尾道では豪商橋本竹下が難民救済事業として慈観寺(尾道市長江一丁目)の本堂の改築を発願した。
この救済事業によりこの時代尾道では一人も餓死者が出なかったことが今に伝わっているが、玉蘊はこの本堂の襖絵を描くことを竹下に依頼されている。
今も慈観寺本堂に玉蘊がその時に描いた「桐鳳凰図」の襖絵が残っている。
雲を金箔で表し、中央から右手にかけて桐の木を配し、左手には平和な世に現れるという純白の鳳凰が悠々と舞っているその姿は彼女が望んだ山陽との幸せな生活を思い描いたものなのであろう。
無論山陽が詠んだ古鏡の詩を絵にしたものである。
山陽のことを未だに慕っている玉蘊の健気さが痛いように伝わってくる。
又、玉蘊が描いた作品として、さらに大作の「雪中の松竹図」が福善寺(尾道市長江一丁目)の本堂正面の襖絵に残っている。

平田玉蘊墓所(持光寺)
この絵は西本願寺御影堂の襖絵に類似しているが、金色の襖一杯に描かれた寒さを耐えている雪中の松と竹と梅に山陽の返事を待ち焦がれていた時の玉蘊の不安な心持と共に「耐寒香梅花」の気魄(きはく)が伝わってくる。
天保十一年(1840)一月、母峯が亡くなった。
七十三歳であった。
峯は山陽との一件や鶴鳴の事を気持ちの上で整理出来ず、以来ずっと拘泥(こうでい)していたので玉蘊はこの母の気持ちを考えると、落ち込んではいられなかった。
むしろ明るく振舞っていた。
それまで玉蘊を世に出し、名を成さしてくれた人達が亡くなった時も確かにそれはそれで辛いものであったが、さすがに母の死位深い無常を覚えたことはなかった。
胸に空洞が出来たような喪失感で何も手に付かなかった。
日本が明治という新しい時代を向かえる為の激しい内戦の始まる安政二年(1855)六月、六十九歳で玉蘊は亡くなっている。
光明寺(尾道市東土堂町)に残されている「富士」が遺作となった。
「女は三界に家なし」と言われ女性が生き辛い封建社会にあっても絵筆一本で生きた玉蘊の墓は福岡屋の菩提寺である持光寺(尾道市東土堂町、浄土宗西山禅林寺派で総本山が京都東山にある永観堂)にある。
持光寺の本堂前の左右には鳳尾蕉軒から運んで植樹したと言われる玉蘊遺愛の蘇鉄が今も青々と繁っている。
本堂向かって左側の墓地の中にある玉蘊の墓標には山陽の弟子であった宮原節庵が伸びやかな書体でその名を刻んでいる。
尾道では毎年六月、この薄幸の閨秀(けいしゅう)作家を偲んで持光寺に於いて「玉蘊忌」が開かれており、大勢の人がお参りに訪れている。

春夏秋冬。季節ごとに尾道は様々な顔を見せてくれます。
歴史的な名所を訪れるのも良し、ゆっくりと街並みを歩きながら心穏やかな時間を過ごすのも良し、美味しい食事を心ゆくまで楽しむも良し。
大人な遊び方ができる尾道において「尾道に来たら、ココだけは行って欲しい!」という、管理にイチオシの観光スポットを紹介しています。詳しくはこちらのページを読んでみてください。
>>管理にオススメの観光スポット